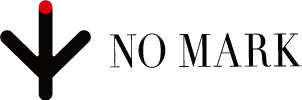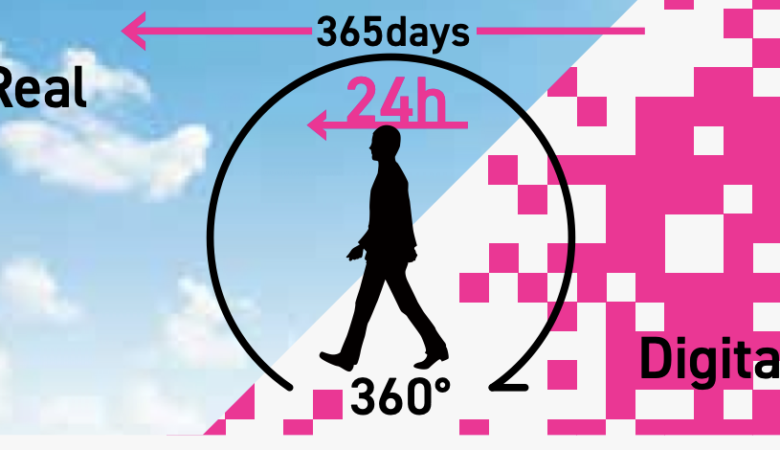無人店舗は、ちょっと品数の多い自動販売機かもしれない
「Amazon GO」が2018年1月にシアトルでオープンして、世間でも話題になった「無人店舗」。すでに中国では無人コンビニ「繽果盒子(Bingo Box)」が複数店舗で展開されており、日本でもオフィス内の無人コンビニの増加や無人店舗の実証実験の活発化など、無人化・省人化は世界的な潮流になっている。
しかし「無人店舗」という言葉がバズワードになっており、バラ色な未来のイメージが先行している感もある。無人店舗というものの現状をしっかりと認識した上で、店舗の未来を考えることが重要だろう。
まず現時点で「無人店舗」と言う場合、「店内に店員を常時配置していない店舗」のことを指すことがほとんどだ。商品陳列や清掃、マテハン業務なども含めバックヤードまで無人化することまでは、想定されていない。つまり店内での接客業務、特に「お会計」をいかに無人で実現するかが肝だと言えるだろう。そしてそのために無人化への取り組みは、セルフレジによってお客様自身に精算してもらうか、Amazon GOのように、認証システムを導入することで精算が自動で済むようにするかの大きく2つに分けられるのだ。
前者は、バーコードの読み取りや袋詰めなどがセルフサービスになるため、いかにお客様の負担を減らすかが重要になってくる。例えばGUは、商品タグにICタグを埋め込むことで、ボックスに服を入れるだけで品数と金額を自動で計算してくれる全自動セルフレジを試験運用している。ドン・キホーテも、ベルトコンベヤーに商品を置くだけで360度からスキャナーで商品を特定できるレジに挑戦している。このセルフレジ方法は、店舗が主体の企業が取り入れることが多い。人手不足や人件費の高騰から、いかにコストを下げていくかを根底にした取り組みだと言えるだろう。

一方で、AmazonなどECをメインにしていた企業が挑戦しようとしているのが、認証システムを使った精算システムである。そもそもECにおいて顧客登録が済んでいるため、こうした方法が導入しやすく、ECとの連携により付加価値を生むことを目指しているのだ。この、商品を選んだらそもそもレジに並ばずにそのまま店を出られるというのは、一度体験すると結構衝撃的である。駅員に切符を切ってもらっていた状態から、今のような自動改札に変わったときに近しい感覚だろう。しかしこちらには、投資対効果の不明瞭さや技術的な精度、さらには多くのカメラやセンサーの設置による不気味さなど、まだまだ解決すべき課題も多い。
このように、今の無人店舗化とは、「お会計」という業務から店員を解放するための取り組みである。もちろんこの「お会計」領域が無人化するだけで、店舗経営において相当なインパクトがあるだろう。しかし言葉を選ばずに言えば、このままの無人店舗化は、品数の多い自動販売機を作っているに過ぎない。こう表現すると、ふわっとしていた無人店舗のイメージが、急に具体的に感じるのではないだろうか。
テクノロジーに、おもてなしはできるのか
テクノロジーに対して「人間味がなくなる」「テクノロジーにおもてなしはできない」というような意見がよくある。しかしそれはテクノロジー活用の一側面しか見ていないからだ。テクノロジーの活用には、大きく2つの目的がある。一つはコストの削減や効率化である。無人化や省人化で、人の排除だなんだと反発が起こるのもこの部分である。そしてもう一つが、付加価値の提供や支払意思額「Willingness to Pay(WTP)」の増大だ。たとえば、2017年10月にAmazonが「Amazon Bar」を銀座に期間限定でオープンした。Amazonならではの豊富な品揃えはもちろん、タブレット端末で「好みのお酒のカテゴリー」や「今の気分」などいくつかの質問に答えると、提供されるお酒が決まるという仕掛けになっていた。リアルの場でもレコメンド機能としてITを活用している良い例だと思う。店舗が提供している価値は、サッと寄ってパッと買えるコンビニエンス性や、みんなが集まれるコミュニティの場、わくわくするショッピング体験だったりと様々だ。AIで来店者の表情を分析し、適切なタイミングで店員が声をかけるようにすることがいいのかもしれないし、ARを活用してお客様が探している商品まで誘導するようにすることがいいのかもしれない。その店舗毎にお客様に求められている価値はなんなのか、そしてECでは提供できない価値はなんなのかをまずは問い直し、その上でその価値を進化させるためにテクノロジーを活用していくべきである。間違った無人店舗化を推し進めて、それならECで買った方が早いし安い、なんてことになると目も当てられない。無人店舗化やテクノロジー活用は、あくまで手段であり目的ではない。お客様にどういった価値提供を実現できるかを考える必要があるのだ。