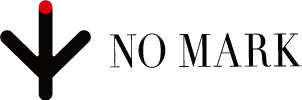製品・サービスを成長させるためには、これまで「Voice of Customer(VOC)=顧客の声」というのがサービスや企業を成長させるために注目すべきファクターとされてきました。特にPRにおいてはVOCだけでなく、どちらかというと「Voice of Media(VOM)=メディアの声」をどれだけ多くできるか、良い論調にできるかが中心的なミッションであると言っても過言ではなかったでしょう。
VOMの重要性は変わらない一方で、マーケターやPRパーソンもヒシヒシと感じているように、たとえメディアに掲載されてもそこまで荷が動かない、つまり売上に繋がらなくなってきているのが現状です(もちろんまだまだテレビの力が強い商材はたくさんあるのですが・・・)。だからこそ広告やPRなどの出面は、マスメディア以外のSNSなども当然カバーしなければならず、タスクはより複雑に高度に煩雑になって来ていると言えます。ただし、統合コミュニケーションなどの言葉が生まれてかなり経ちますが、各メディアを独立したものと捉えて、それぞれにどう対応するか、そして全体としてメディアミックスするためにどうするか、どういうコミュニケーションをとっていくかということが主流です。しかし、テクノロジーの進化がもたらした新しい“声”の登場が、今、コミュニケーション戦略を根底から変えようとしているのではないでしょう。
それが、「Voice of AI(VOAI)」です。
AIがブランドの情報を再構成し、AIの“声”で社会に発信する時代。その波に備えるために、企業は新たな概念「VOAI」を理解し、PRのあり方を再設計する必要があるのです。
生成AIが「メディア」になる時代
ChatGPTやGemini、Claudeなど、いわゆる大規模言語モデル(LLM)は、膨大なテキストをもとに質問に答えたり、要約を行ったりします。その過程で、企業が公開したプレスリリースやブログ、ニュース記事などを参照し、AIがブランドや製品について説明する——いわば「AIが語るブランド」が生まれていると言えるのです。
従来のPRが「”人間の”記者や読者にどう伝えるか」を中心に設計されていたのに対し、今後は「AIにどう語らせるか、AIがどう再構成するか」を想定した情報発信をすることが、ブランドイメージを左右する要素となるのです。つまり、AIが発する“声”も、PRとしてのコミュニケーション設計の一部と見なすべきなのです。
「Voice of AI(VOAI)」とは何か?
改めて、VOAI(Voice of AI)とは、
企業やブランド、メディアなどあらゆる発信情報が直接世の中に届けられるのではなく、AIによって再構成・再解釈され、他の情報と合わせて新たなAIによる”声”として作られ、最適とAIが判断したタイミングや文脈で世の中に届けられる。
ということです。
AIが“情報の媒介者”として存在感を増す時代において、VOAIはブランドマネジメントにとって大事なファクターとなるのは間違いないでしょう。今まではある程度、自社のコントロール下においてWPO(Web Presence Opitimization:情報環境の最適化)を良くすることが可能でした。もちろんPRパーソンは、報道部や社会部から問い合わせがあると緊張しますし、あらゆるメディアで自社が望むような論調にできるということは不可能です。しかしそれでもある程度自衛ができましたし、信頼のおけるメディアは必ず裏取りがあるため、どんな場合でも自社の声を届けることが可能ではありました。
しかし、AIが情報発信者と生活者の間に入ることになると、様々な情報ソースからつまみ食い形式で取り上げられるので、どういう文脈で取り上げられるか、他のどういうコンテンツと並ぶのか、どこの部分が取り上げられるのかなどが未知数になります。ウェブ検索だけでなくあらゆる情報提供の場にAIが関与することになるとすると、そうしたリスクを最小化するとともに、逆にAIに取り上げられるためにどうすれば良いのかを考える必要があるのです。
WPOもAIを真ん中に、テレビなどのマスメディアやウェブメディアでの露出、SNSでの口コミ、プレスリリースや自社記事などのオウンドメディアでの発信、、、などのPR施策を配置していくことが重要になってくるのではないでしょうか。
VOAI × LLMOによる新しいPR戦略
ここで重要になるのが「LLMO(Large Language Model Optimization)」です。AIO(AI Optimization)などとも非常に近しい言葉で厳密にはそれぞれに違いはあるとも言えますが、そこまで現時点では気にしなくても良いのではないかと考えています。そのためここではAIOやAEO(Answer Engine Optimization)、GEO(Generative Engine Optimization)などもLLMOとして一括りにしています。
LLMOは、検索のためのSEO(Search Engine Optimization)に対して、AIが参照・回答するためのコンテンツ最適化の手法を指します。つまり、検索エンジンではなく、 「AIがどのように学び・引用し・語るか」をコントロールするための工夫です。
LLMOの主な目的は以下の通りです
- AIに正確な情報を学習させる(誤った再構成を防ぐ)
- AIが理解しやすい構造で発信する(構造化データや明確な文脈設計)
- ブランドの世界観をAIに浸透させる(一貫した語り口の維持)
VOAIの実現には、まさにこのLLMOの理解と実践が必要になってきます。
そうした時にSEOの現状は非常に参考になります。というのも、下記の記事のように現時点ではAIが取り上げる内容のうちのある程度が、検索上位に表示されるコンテンツからであり、LLMO対策として多くの企業がやるべきことは、SEO対策と同じ部分が多いでしょう。(重複率が高い低いは業種ごとに傾向があり、YMYLコンテンツや教育、保険は重複率が高く、Eコマースは重複率が低いようです。)
https://www.searchenginejournal.com/google-ai-overviews-overlaps-organic-search-by-54/557317/
今まではSEO対策として出すコンテンツと、自社が伝えたいコンテンツを分けている企業が多くありました。その理由として、後者は制作に時間がかかるのとSEOのキーワードを入れようとするとどうしても初心者向けの要素が入るため、執筆者(もしくは経営者や事業責任者などのインタビュイー)が嫌う傾向があったためです。
しかし最近では、SEOの重要性の理解が進み(自社が伝えたいコンテンツを発信したらSEOコンテンツに比べて圧倒的にビュー数がない、という状況に気付いてから方向転換するということもありますが。)、土台(キーワードや構成など)はSEOを意識して作りつつ、内容についてはハイレベルな(読み応えのある)内容にするハイブリッド型が増えてきています。プロの記者や編集者を自社に招き入れるケースも増えています。
PRにおける情報発信においても、
- プレスリリースや記事などは、情報発信AIが理解しやすい構造にする
- どういう文脈(質問)で自社やサービス・製品が登場すると良いか、逆に登場して欲しくない文脈(質問)は何なのかを明確にする
- AIプラットフォーム上でブランドや狙っているキーワードについてどのように言及されているかを定期的にモニタリング
- とにかくコンテンツが少ないキーワードにおいては情報発信を積極的にする
- 競合コンテンツが多いキーワードについてはクオリティの高いコンテンツ発信にする
- AIが拾って来やすいメディア・サイトをチェックする
などは必要になるでしょう。
まだまだAI自体が急激に成長している段階のため、焦って取り組む必要はないと考えています。ただし新しいメディアやプラットフォームができたときに、最初に取り組んだ人や企業は、やはり有利であることは確かです。そのため、常に自分自身でAI関連については使ってみて、AIの現在地は把握しておくようにした方が良いでしょう。